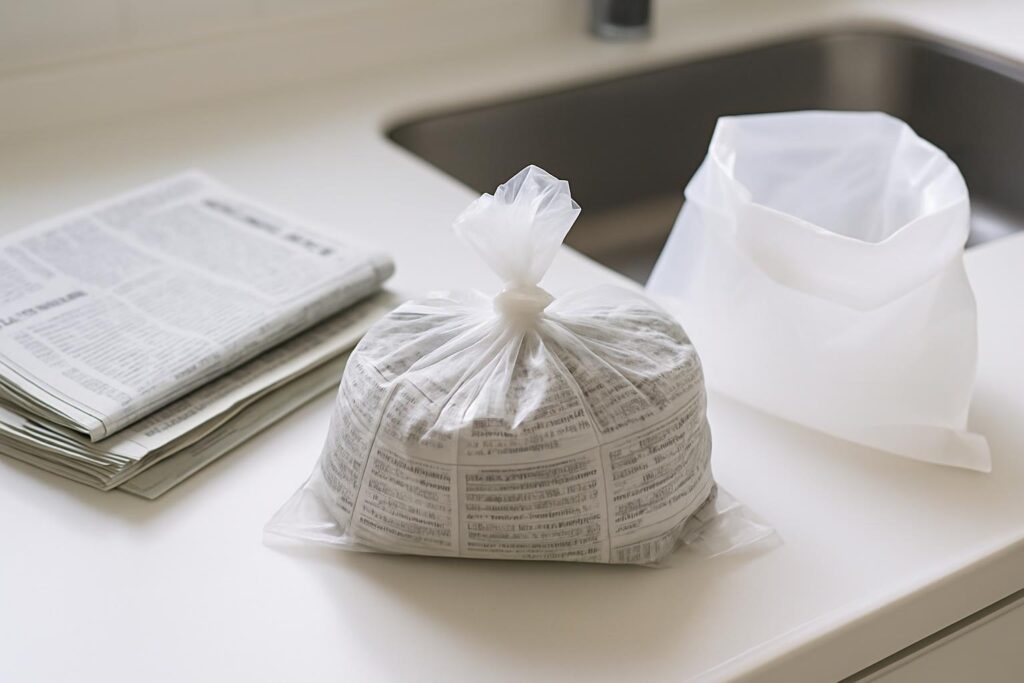秋になると何となく心が沈んだり、悲しい気持ちになったりしませんか?東洋医学では、その原因の一つを「乾燥」と捉えています。この記事では、秋の心の不調と乾燥の関係性を薬膳の視点から詳しく解説。
乾燥による悲しみを癒すための具体的な薬膳レシピやおすすめ食材、今日から実践できる心のケア方法をご紹介します。薬膳の知恵で心と体に潤いを与え、秋の季節を穏やかに過ごすヒントを見つけましょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
1. 秋になると悲しい気持ちになるのはなぜ?その心の変化に寄り添う
夏の賑やかさが終わりを告げ、空が高く澄み渡り、涼しい風が吹き始める秋。多くの人にとって過ごしやすい季節である一方で、「なんとなく寂しい」「心が沈む」といった感情を抱く方も少なくありません。この章では、なぜ秋になると心が揺らぎやすくなるのか、その背景にある心の変化と、近年注目されている「秋うつ」と「乾燥」の意外な関係性について掘り下げていきます。
1.1 秋の気配とともに感じる心の変化
秋は、一年の中でも特に感傷的な気持ちになりやすい季節と言われています。日中の日差しが弱まり、夕暮れが早くなることで、私たちは無意識のうちに自然の変化を感じ取っています。この季節の移ろいが、私たちの心に様々な影響を与えるのです。
- 日照時間の減少:夏に比べて日照時間が短くなることで、脳内で分泌される神経伝達物質の一つであるセロトニンの量が減少しやすいと言われています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心の安定や気分の調整に深く関わっています。その分泌が減ることで、気分の落ち込みや意欲の低下を感じやすくなることがあります。
- 気温と湿度の変化:徐々に気温が下がり、空気が乾燥し始める秋。身体は冬に向けて準備を始めますが、この急激な変化に自律神経が対応しきれず、バランスを崩すことがあります。これにより、身体のだるさや倦怠感とともに、精神的な不安定さを感じやすくなることもあります。
- 季節の節目:夏の終わりは、楽しい思い出とともに少しの寂しさを伴います。そして、冬へと向かう準備期間である秋は、「終わり」や「変化」を意識させ、内省的になったり、過去を振り返ったりする機会が増えるため、心がセンチメンタルになりやすい傾向があります。
このように、秋の訪れは私たちの心と体に様々な影響を与え、普段は感じないような心の揺らぎや悲しみを引き起こすことがあるのです。
1.2 「秋うつ」と乾燥の関係性
「秋になると憂鬱になる」「やる気が出ない」といった症状は、しばしば「秋うつ」と表現されることがあります。これは医学的な診断名ではありませんが、季節性感情障害(SAD)の一種として知られる、特定の季節にのみ発症するうつ病と似た症状を指すこともあります。一般的には日照時間の減少が主な原因とされていますが、東洋医学の観点からは、もう一つ見過ごせない要因があります。それが「乾燥」です。
西洋医学的な観点では、秋うつの主な原因として以下の点が挙げられます。
| 要因 | 心身への影響 |
|---|---|
| 日照時間の減少 | セロトニン分泌量の低下、気分の落ち込み、意欲低下 |
| メラトニン分泌量の増加 | 過眠傾向、だるさ、倦怠感 |
| 気温・気圧の変化 | 自律神経の乱れ、頭痛、肩こり、身体の不調 |
しかし、東洋医学では、秋の「乾燥」が心の不調に深く関わると考えられています。肌の乾燥や喉の渇きといった目に見える変化だけでなく、私たちの体内の「潤い」が不足することで、心にも影響が及ぶとされているのです。具体的には、東洋医学における「肺」の機能と心の状態が密接に結びついており、秋の乾燥は「肺」にダメージを与え、それが心の悲しみや憂鬱感につながると考えられています。
この章では、一般的な秋の心の変化と「秋うつ」の概念を理解した上で、次の章からは東洋医学の視点から「乾燥」が心に与える影響、そしてその対策としての「薬膳」の力について詳しく解説していきます。
2. 東洋医学が語る「秋の乾燥」と心のつながり
2.1 薬膳の考え方から見る秋と「肺」の関係
東洋医学、特に薬膳の考え方では、自然界の移り変わりと私たちの体の変化は密接につながっていると捉えます。季節の巡りを「五行」という考え方で分類し、秋は「金」に属し、体の臓器では「肺」と深い関係があるとされています。
この「肺」は、西洋医学でいう呼吸器系だけでなく、東洋医学ではより広範な役割を担います。具体的には、呼吸を司り、体内の「気」を巡らせる重要な働きがあります。また、皮膚や毛髪の潤いを保ち、汗腺の開閉を調整することで体温調節にも関わると考えられています。さらに、悲しみや憂鬱といった感情とも深く結びついているのが特徴です。
秋は空気が乾燥し始める季節です。東洋医学では、この乾燥した「燥邪(そうじゃ)」が、特に「肺」にダメージを与えやすいと考えます。肺が乾燥すると、その本来の機能が低下し、体だけでなく心にも影響を及ぼし始めるのです。
2.2 肺の乾燥が引き起こす心と体の不調
肺が乾燥すると、まず身体的な不調として現れることがあります。例えば、空咳が出やすくなったり、喉や鼻の乾燥、皮膚のカサつき、便秘などが挙げられます。これらは、肺が司る呼吸器系や皮膚、そして水分代謝の機能が低下しているサインです。
そして、身体の不調と並行して、心にも影響が及びます。東洋医学では「肺は気を主る」と言われるように、肺は体全体の「気」の巡りをコントロールする役割を担っています。肺が乾燥して機能が低下すると、気の巡りが滞りやすくなり、気力の低下や倦怠感、集中力の散漫といった症状が現れることがあります。
さらに、肺と感情のつながりから、悲しみや憂鬱感、感傷的になりやすい、イライラしやすいといった心の不調が表面化することもあります。秋の物悲しさやセンチメンタルな気分は、この肺の乾燥が背景にあると東洋医学では考えられているのです。
2.3 「気」「血」「津液」のバランスと心の安定
東洋医学では、私たちの体は「気(き)」「血(けつ)」「津液(しんえき)」という三つの要素がバランス良く巡ることで健康が保たれると考えます。これらのバランスが崩れると、心身に様々な不調が生じます。
| 要素 | 役割 | 秋の乾燥による影響 | 心の安定への影響 |
|---|---|---|---|
| 気(き) | 生命活動のエネルギー源、体を温め、臓腑の機能を促進する。 | 肺の乾燥により気の巡りが滞り、不足しやすくなる。 | 気力低下、倦怠感、気分が落ち込む、意欲の減退。 |
| 血(けつ) | 全身に栄養と潤いを供給し、精神活動を支える。 | 津液の不足により、相対的に血の濃縮や巡りの悪化を招くことがある。 | 精神不安、不眠、イライラ、感情の不安定さ。 |
| 津液(しんえき) | 体内のあらゆる水分(体液、潤滑液)で、臓腑や皮膚、関節などを潤す。 | 秋の乾燥により最も消耗されやすい。 | 体全体の潤い不足、口渇、皮膚の乾燥、心の焦燥感。 |
特に秋の乾燥は、体内の「津液」を消耗させやすい季節です。津液が不足すると、全身の潤いが失われるだけでなく、「気」や「血」の巡りにも悪影響を及ぼします。例えば、津液が不足すると血が濃くなり、巡りが悪くなる「血瘀(けつお)」の状態を招くこともあります。また、気は津液を運ぶ役割も担うため、津液が不足すると気の巡りも滞りやすくなります。
このように、「気」「血」「津液」のどれか一つでもバランスが崩れると、連鎖的に他の要素にも影響が及び、結果として心の安定が損なわれ、悲しみや不安感が増幅されると考えられています。秋の悲しい気持ちは、まさにこの三つのバランス、特に津液の不足と肺の乾燥が引き起こす東洋医学的なサインなのです。
3. 乾燥が原因の悲しい気持ちを癒す薬膳の力
秋の深まりとともに感じる心のざわつきや悲しい気持ちは、東洋医学の視点では「乾燥」と深く関連していると考えられます。特に、呼吸器系を司る「肺」が乾燥することで、心にも影響が及ぶことは前章で触れた通りです。ここでは、薬膳の知恵を借りて、この乾燥からくる心の不調をどのように癒し、穏やかな心を取り戻すことができるのかを具体的に見ていきましょう。
3.1 薬膳で「潤い」を補い心を整える
薬膳の基本的な考え方は、「体は食べたもので作られる」というものです。季節や体質、体調に合わせて食材を選び、日々の食事を通して体のバランスを整えることで、心身の健康を維持します。秋の乾燥による心の不調に対しては、特に「潤いを補う(滋陰潤燥)」ことに重点を置いた薬膳が有効です。
東洋医学において「陰」は体の潤いや冷却作用を指し、この陰が不足すると乾燥が進み、熱がこもりやすくなります。秋は自然界の陰の気が減少し、乾燥が進む季節であるため、体内の陰液(津液)も消耗しやすくなります。津液の不足は、肺だけでなく、心や肝といった他の臓腑にも影響を及ぼし、精神的な不安定さにつながることがあります。
薬膳では、乾燥した体を内側から潤し、心に落ち着きをもたらす食材を積極的に取り入れることで、「肺の働きを助け、気の巡りを整え、心を安定させる」ことを目指します。これにより、悲しい気持ちや憂鬱な気分が和らぎ、心身ともに健やかな状態へと導かれるのです。
3.2 秋の悲しみを和らげる薬膳食材の選び方
秋の乾燥による悲しい気持ちを癒すためには、具体的にどのような食材を選べば良いのでしょうか。薬膳では、食材が持つ五味(酸・苦・甘・辛・鹹)や五性(寒・涼・平・温・熱)、そしてその効能を考慮して選びます。
特に秋におすすめなのは、体を潤し、肺を滋養する作用(滋陰潤肺)を持つ食材や、精神を安定させる作用(安神作用)を持つ食材です。また、消化吸収を助け、気血の生成を促す食材も大切です。
3.2.1 潤いをもたらす代表的な食材
白い色をした食材や、粘り気のある食材には、体を潤す働きを持つものが多いとされています。これらは、乾燥した肺を優しく潤し、体内の津液を補うのに役立ちます。
- 梨:体を潤し、熱を冷まし、咳を鎮める作用があります。特に肺の乾燥による喉の不調や空咳に効果的です。
- 白きくらげ:「貧者の燕の巣」とも呼ばれ、強い滋陰潤肺作用を持ちます。肌や粘膜を潤し、精神を安定させる効果も期待できます。
- 蓮根:生食では体を冷まし、加熱すると体を温める性質を持ちます。肺を潤し、止血作用もあります。精神安定にも良いとされます。
- 山芋(長芋):消化吸収を助け、胃腸を丈夫にする働きがあります。滋養強壮効果が高く、肺や腎を補い、体全体の潤いを保ちます。
- 百合根:肺を潤し、咳を鎮めるほか、精神を安定させる安神作用に優れています。不眠やイライラ、悲しい気持ちの緩和に役立ちます。
- 豆腐・豆乳:体を潤し、熱を冷ます作用があります。消化しやすく、良質なタンパク質源でもあります。
3.2.2 心を落ち着かせる食材
精神を安定させ、安眠を促す食材も、秋の悲しい気持ちを和らげる上で重要です。
- くるみ:脳の働きを助け、腎を補い、肺を潤します。安神作用もあり、不眠や物忘れの改善にも良いとされます。
- 松の実:体を潤し、腸を滑らかにするほか、精神を落ち着かせる作用があります。滋養強壮にも優れています。
- 竜眼肉(リュウガンニク):心を補い、精神を安定させる代表的な食材です。不眠や動悸、物忘れ、疲労感の改善に用いられます。
- なつめ:気を補い、血を養い、精神を安定させる効果があります。消化器系の働きを助け、体全体を健やかに保ちます。
3.2.3 その他、気血を補う食材
潤いだけでなく、気(エネルギー)や血(栄養)を補うことも、心身のバランスを整える上で不可欠です。
- 鶏肉・豚肉:体を温め、気血を補い、滋養強壮に役立ちます。特に豚肉は体を潤す作用も持ちます。
- 卵:気血を補い、体を潤します。精神安定にも良いとされます。
- 米・もち米:脾胃(消化器系)を健やかにし、気血の生成を助ける主食です。
- はちみつ:肺を潤し、咳を鎮めるほか、体を滋養する働きがあります。
これらの食材を日々の食事に意識的に取り入れることで、内側から乾燥対策を行い、心に潤いと落ち着きをもたらすことができます。食材の組み合わせや調理法を工夫することで、より効果的に薬膳の力を活用できるでしょう。
| 分類 | 代表的な食材 | 主な薬膳的効能 |
|---|---|---|
| 滋陰潤肺(潤い補給) | 梨、白きくらげ、蓮根、山芋、百合根、豆腐、豆乳、豚肉、鴨肉、はちみつ | 肺の乾燥を潤し、体内の津液を補う。肌や粘膜の乾燥改善。 |
| 安神作用(精神安定) | 百合根、くるみ、松の実、竜眼肉、なつめ、卵 | 心を落ち着かせ、精神的な不安や不眠を和らげる。 |
| 補気養血(気血補給) | 鶏肉、豚肉、卵、米、もち米、なつめ、山芋 | 気力や体力を補い、血の巡りを良くして、体全体を健やかに保つ。 |
4. 心を潤す薬膳レシピ 秋の悲しい気持ちを和らげる一皿
秋の乾燥は、私たちの心と体に様々な影響を与えます。特に「肺」の潤いが不足すると、悲しい気持ちや憂鬱感につながりやすいと東洋医学では考えられています。ここでは、肺を潤し、心に安らぎをもたらすことを目的とした薬膳レシピをご紹介します。日々の食事に薬膳の知恵を取り入れ、内側から心身のバランスを整えましょう。
4.1 梨と白きくらげの潤いスープ
梨と白きくらげは、肺を潤し、体の乾燥を和らげる代表的な食材です。特に白きくらげは「銀耳(ぎんじ)」とも呼ばれ、古くから滋養強壮や美容に良いとされてきました。このスープは、のどの乾燥や空咳、そして秋の物悲しさを感じやすい方におすすめです。
4.1.1 材料(2人分)
| 食材名 | 分量 |
|---|---|
| 梨(和梨または洋梨) | 1/2個 |
| 乾燥白きくらげ | 5g |
| クコの実 | 小さじ1 |
| 氷砂糖 | 大さじ1〜2(お好みで調整) |
| 水 | 400ml |
4.1.2 作り方
- 乾燥白きくらげはたっぷりの水に30分ほど浸して戻し、硬い石づき部分を取り除いて一口大にちぎります。
- 梨は皮をむき、芯を取り除いて食べやすい大きさに切ります。
- 鍋に水、白きくらげ、梨、クコの実を入れ、中火にかけます。
- 沸騰したら弱火にし、アクを取りながら20分ほど煮込みます。白きくらげがとろりとするまで煮込むのがポイントです。
- 氷砂糖を加えて溶かし、味を調えたら完成です。温かいうちにお召し上がりください。
4.1.3 薬膳ポイント
- 梨:肺を潤し、熱を冷まし、のどの渇きや咳を和らげます。
- 白きくらげ:滋陰潤肺(しにいんじゅんぱい)作用があり、体の潤いを補い、乾燥による不調を改善します。
- クコの実:滋養強壮、目の疲れの緩和、そして精神を安定させる効果も期待できます。
4.2 鶏肉と蓮根の滋養煮込み
秋は「肺」だけでなく「脾(ひ)」の働きも整えることが大切です。脾は消化吸収を司り、気(エネルギー)や血(栄養)を作り出す源。脾の働きが低下すると、気血不足になり、気力が湧かない、気分が落ち込むといった症状につながることがあります。この煮込みは、脾胃を健やかにし、体を内側から温めて滋養する一品です。
4.2.1 材料(2人分)
| 食材名 | 分量 |
|---|---|
| 鶏もも肉 | 1枚(約250g) |
| 蓮根 | 150g |
| 人参 | 1/2本 |
| 生姜 | 1かけ |
| だし汁 | 300ml |
| 醤油 | 大さじ2 |
| みりん | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ1 |
4.2.2 作り方
- 鶏もも肉は一口大に切り、軽く塩こしょう(分量外)を振ります。蓮根は皮をむいて1cm厚さのいちょう切り、人参は乱切りにします。生姜は薄切りにします。
- 鍋に少量の油(分量外)を熱し、鶏肉の皮目を下にして焼き色がつくまで焼きます。
- 蓮根、人参、生姜を加えて軽く炒め合わせます。
- だし汁、醤油、みりん、酒を加え、沸騰したらアクを取り、蓋をして弱火で20分ほど煮込みます。
- 蓮根が柔らかくなり、味が染み込んだら完成です。
4.2.3 薬膳ポイント
- 鶏肉:補気血(ほきけつ)作用があり、気を補い、体を温めて疲労回復を助けます。
- 蓮根:健脾益胃(けんひえきい)作用があり、消化機能を高め、気血の生成を助けます。精神を安定させる効果も期待されます。
- 人参:脾胃を健やかにし、気を補い、目の疲れを和らげます。
- 生姜:体を温め、消化を助け、気血の巡りを良くします。
4.3 その他のおすすめ食材と簡単な薬膳レシピ
特別な調理をしなくても、日々の食事に意識して取り入れるだけで、薬膳の効果を享受できる食材はたくさんあります。秋の乾燥対策と心の安定に役立つ食材を知り、手軽な方法で薬膳を取り入れてみましょう。
4.3.1 秋の潤いを補う食材リスト
以下の食材は、肺を潤し、乾燥による不調や心の不安定さを和らげるのに役立ちます。
| 食材名 | 主な薬膳効果 | 取り入れ方のヒント |
|---|---|---|
| 山芋(長芋) | 滋養強壮、健脾益気、潤肺 | すりおろしてとろろご飯、短冊切りで和え物、炒め物 |
| 百合根 | 潤肺止咳、清心安神(せいしんあんじん) | 茶碗蒸し、スープ、煮物、天ぷら |
| 杏仁(あんずの種) | 潤肺止咳、通便 | 杏仁豆腐、お粥に入れる(加熱して少量) |
| ハトムギ | 健脾利湿、清熱排膿 | お粥、スープ、ご飯と一緒に炊く |
| 銀杏 | 斂肺定喘(れんぱいていぜん)、益腎 | 茶碗蒸し、炊き込みご飯、炒め物 |
| 柿 | 潤肺生津、清熱 | 生食、スムージー、サラダ |
| 蜂蜜 | 潤肺止咳、滋養強壮 | 飲み物に入れる、ヨーグルトにかける、料理の甘味料 |
| 豆乳 | 滋陰潤燥、補気 | 温めて飲む、スープ、鍋物 |
| ごま | 滋陰潤燥、補肝腎 | 和え物、ふりかけ、ドレッシング |
| くるみ | 補腎、潤肺、通便 | おやつ、サラダ、パンに入れる |
4.3.2 手軽にできる薬膳レシピのヒント
- 温かいお粥:消化に優しく、体を温めます。上記リストの山芋やハトムギ、銀杏などを加えて炊けば、さらに滋養効果が高まります。
- 具だくさんスープ:旬の野菜と、鶏肉やきのこ、豆腐などを入れたスープは、手軽に栄養が摂れ、体を温めます。
- 蒸し料理:食材の栄養を逃がさず、油を使わないためヘルシーです。魚や鶏肉、野菜を蒸して、ポン酢や薬味でシンプルに。
- フルーツを使ったデザート:梨や柿などの旬の果物をそのまま食べるだけでなく、温めてコンポートにしたり、ヨーグルトと合わせたりするのもおすすめです。
- ホットドリンク:生姜湯やハーブティー、蜂蜜を加えた温かい豆乳などは、手軽に体を温め、心を落ち着かせる効果が期待できます。
5. 薬膳と合わせて実践したい心のケア
秋の悲しい気持ちは、乾燥による体内のアンバランスだけでなく、日々の生活習慣や心の状態も深く関わっています。薬膳で体の内側から整えることに加え、心身のケアを総合的に行うことで、より効果的に穏やかな気持ちを取り戻すことができます。ここでは、薬膳と合わせて実践したい具体的なセルフケアの方法をご紹介します。
5.1 秋の乾燥対策と生活習慣の見直し
秋の乾燥は、肌や呼吸器だけでなく、体内の「津液(しんえき)」不足につながり、心の不安定さを招くことがあります。日々の生活の中で、乾燥から体を守り、心身のバランスを整える習慣を取り入れましょう。
5.1.1 体を内側から潤す水分補給の工夫
ただ冷たい水をがぶ飲みするのではなく、体を冷やさずに効率よく潤いを補給する工夫が大切です。温かい飲み物や、水分を多く含む食材を意識的に摂り入れましょう。
| 飲み物の種類 | おすすめポイント |
|---|---|
| 白湯 | 体を温めながら、内臓の働きを助け、潤いを巡らせます。ゆっくりと時間をかけて飲むのがポイントです。 |
| 温かいハーブティー | カモミールやルイボスティーなど、ノンカフェインでリラックス効果のあるものがおすすめです。香りで心も落ち着きます。 |
| 旬の果物 | 梨や柿、ぶどうなど、秋の果物は水分やビタミン、ミネラルが豊富です。生のままで摂取することで、効率よく潤いを補給できます。 |
| スープや味噌汁 | 食事から水分と栄養を同時に摂ることで、体の内側からじんわりと温まり、潤いを補給できます。 |
5.1.2 乾燥から肌と呼吸器を守る環境づくり
秋の乾燥は、肌のかさつきだけでなく、喉や鼻といった呼吸器系の粘膜にも影響を与え、不快感や体の不調を引き起こしやすくなります。快適な環境を整えることで、心身のストレスを軽減しましょう。
- 加湿器の活用:室内の湿度は50~60%を目安に保つと良いでしょう。特に就寝時は、喉や鼻の乾燥を防ぎ、安眠にもつながります。
- マスクの着用:外出時や就寝時にマスクを着用することで、喉や鼻の粘膜の乾燥を防ぎ、外部からの刺激から守ることができます。
- 適切な室温管理:暖房を使いすぎると空気が乾燥しやすくなります。加湿と合わせて、室温は適度な温度に保ちましょう。
- 入浴で全身を潤す:湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、皮膚からの水分蒸発を防ぎつつ、リラックス効果も高まります。入浴剤に保湿成分が含まれているものを選ぶのも良いでしょう。
5.1.3 質の良い睡眠で心身の回復を促す
睡眠は、心と体の疲れを癒し、自律神経のバランスを整えるために不可欠です。秋の夜長を活かして、質の良い睡眠を心がけましょう。
- 規則正しい睡眠サイクル:毎日同じ時間に就寝・起床することで、体内時計が整い、質の高い睡眠につながります。
- 寝室環境の整備:寝室は暗く静かに保ち、適度な室温と湿度(加湿器活用)を保ちましょう。寝具も肌触りの良いものを選ぶと快適です。
- 寝る前のリラックス習慣:就寝前の1~2時間は、スマートフォンやPCの使用を控え、温かい飲み物を飲む、軽い読書をする、ストレッチをするなど、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。
5.2 心を穏やかに保つセルフケア
秋の悲しい気持ちに寄り添い、心を穏やかに保つためには、日々の生活に意識的なセルフケアを取り入れることが有効です。五感を刺激するアロマや、体を動かすことで、心のバランスを整えましょう。
5.2.1 リラックス効果を高めるアロマテラピー
香りは脳に直接働きかけ、感情や気分に大きな影響を与えます。アロマテラピーを上手に取り入れることで、秋の悲しい気持ちを和らげ、心を穏やかに保つことができます。
| おすすめのアロマ | 効果・効能 | 使用方法 |
|---|---|---|
| ラベンダー | 鎮静作用が高く、不安やストレスを和らげ、安眠を促します。 | 芳香浴(アロマディフューザー)、お風呂に数滴垂らす、枕元にティッシュに垂らして置く。 |
| ベルガモット | 気分を高揚させ、リフレッシュ効果があります。うつうつとした気持ちを明るくします。 | 芳香浴、バスソルトに混ぜて入浴。 |
| サンダルウッド | 心を落ち着かせ、瞑想的な気分に導きます。精神的な安定を促します。 | 芳香浴、キャリアオイルに希釈してマッサージ。 |
| ゼラニウム | ホルモンバランスを整える作用があると言われ、気分のムラを和らげます。 | 芳香浴、キャリアオイルに希釈してマッサージ。 |
5.2.2 心と体をほぐす軽い運動とストレッチ
適度な運動は、血行を促進し、ストレスホルモンの分泌を抑え、幸福感をもたらすエンドルフィンを分泌させます。激しい運動でなくても、心と体をほぐす軽い運動を取り入れましょう。
- ウォーキングや散歩:特に日中の時間帯に、太陽の光を浴びながら行うことで、セロトニンの分泌を促し、気分を安定させます。自然の中を歩くのも良いでしょう。
- ヨガやピラティス:呼吸に意識を向けながら体を動かすことで、心身のバランスを整え、リラックス効果を高めます。
- ストレッチ:就寝前や起床時に、ゆっくりと全身を伸ばすことで、筋肉の緊張がほぐれ、血行が促進されます。特に首や肩、背中のストレッチは、自律神経のバランスを整えるのに役立ちます。
5.2.3 デジタルデトックスで心の休息を
スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスは、私たちの生活を便利にする一方で、知らず知らずのうちに心に負担をかけていることがあります。意識的にデジタルデバイスから離れる時間を作ることで、心の休息を促しましょう。
- 就寝前の使用を控える:ブルーライトは睡眠の質を低下させます。寝る1~2時間前からは、デジタルデバイスの使用を避けましょう。
- 「オフ」の時間を作る:週末の数時間、または毎日決まった時間帯は、通知をオフにし、デジタルデバイスに触れない時間を作りましょう。その時間は、読書や趣味、家族との会話などに充ててみてください。
- 自然と触れ合う:デジタルデバイスから離れ、公園を散歩したり、ガーデニングをしたりと、自然の中で過ごす時間は、心をリフレッシュさせ、ストレス軽減に繋がります。
6. まとめ
秋に悲しい気持ちになるのは、東洋医学では乾燥が原因で「肺」の機能が低下し、心のバランスが乱れやすくなると考えられます。この「肺」の乾燥は、悲しみや気分の落ち込みといった心の不調を引き起こすことがあります。薬膳は、梨や白きくらげなど「潤い」を補う食材を取り入れることで、体の内側から乾燥を和らげ、心を穏やかに保つ手助けとなります。日々の食事に薬膳を取り入れ、生活習慣を見直すことで、秋の悲しみを乗り越え、心身ともに健やかに過ごしましょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
気になる記事、見つかるかも?
-

もう臭わない!ゴミを減らす・ムダを出さないアイデア:生ゴミは「新聞紙+ポリ袋」で包み、水気カットで臭い防止
生ゴミの嫌な臭いや家庭ゴミの多さに悩んでいませんか?この記事を読めば、生ゴミの臭いを劇的に減らす「新聞紙+ポリ袋」を使った水気カットの秘訣が分かります。さら… -



12月から始める免疫UP!風邪・インフルが増える冬の家族薬膳。子どもと大人が一緒に食べられる自宅でできる“免疫スープ”
12月から本格化する風邪やインフルエンザの流行。家族みんなで元気に冬を乗り切りたいけれど、毎日の食事で何ができるか悩んでいませんか? この記事では、なぜ今「冬の… -



時短&節約!夏野菜を賢く長持ちさせる冷凍保存術ガイド
旬の夏野菜を美味しく長持ちさせたいけれど、使いきれずに傷ませてしまうことはありませんか?この記事では、夏野菜を賢く冷凍保存し、鮮度を保ちつつ、時短と節約を叶… -



【冷蔵庫・保存テクニック】忙しいあなたへ!<週末仕込み>切った根菜を水にさらして冷蔵 → 平日すぐ使える賢い時短テクニック
「平日の料理をもっと楽にしたい」そんなあなたへ。この記事では、週末に切った根菜を水にさらして冷蔵するだけで、鮮度を保ちつつ平日すぐに使える時短テクニックを徹… -



乾物・粉物の湿気対策はこれで解決!ニトリの「自立する保存袋」で賢く湿気から守る方法
「小麦粉が固まる」「乾物がカビる」など、乾物や粉物の湿気問題にうんざりしていませんか?本記事では、そんな悩みを解決するニトリの「自立する保存袋」の魅力と活用… -



夏土用は“食べて養生”が正解!胃腸が疲れやすい夏の「脾を守る」消化に優しい1週間薬膳献立~蒸し料理・スープごはん組み合わせのモデルプラン
夏土用は、暑さや冷たいものの摂りすぎで胃腸が疲れやすい時期です。本記事では、この時期に大切な「脾(ひ)」を労わり、消化に優しい「食べて養生」の薬膳献立を提案…