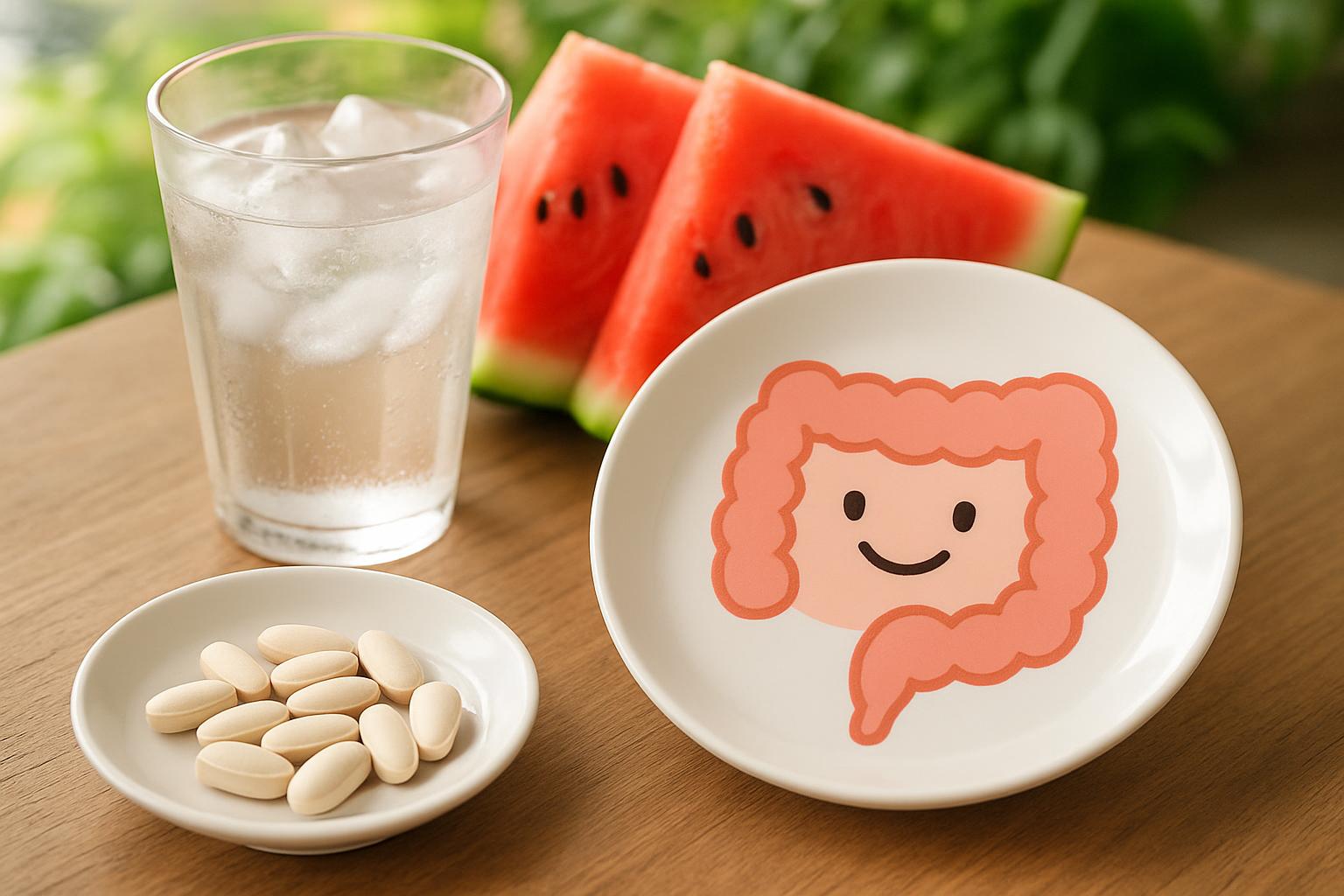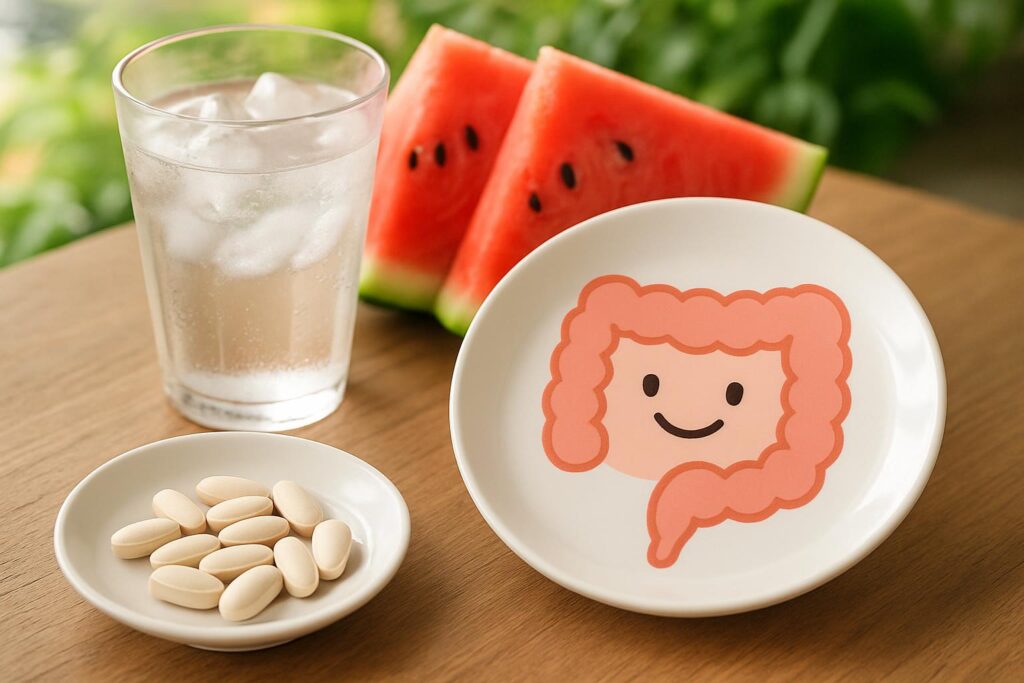
夏の暑さで冷たいものを摂りすぎ、腸が冷えて「腸疲れ」を感じていませんか?お腹の不調やだるさは、冷えすぎた腸からのSOSかもしれません。この記事では、なぜ夏に腸が冷えるのかそのメカニズムを解説し、腸を温める薬膳の知恵をご紹介します。長ねぎ、鮭、にら、しょうがなど「温性」食材をたっぷり使った、胃腸を守る夕食レシピで、冷えすぎた腸を内側から温め、夏の不調を解消し、元気を取り戻す具体的な方法が分かります。今日からできる温活で、健やかな体を目指しましょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
夏の“腸疲れ”サインに気づいていますか
知らず知らずのうちに冷える夏の腸
夏の暑い日々に、私たちの体は知らず知らずのうちに冷えにさらされています。外気温が高いため、つい冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎたり、エアコンの効いた部屋で長時間過ごしたり、シャワーだけで済ませて湯船に浸からなかったりしていませんか? これらの夏の習慣が、実はあなたの腸を内側から冷やしている可能性が高いのです。
体は冷えを感じると、その冷えから身を守ろうとします。しかし、冷たいものの摂りすぎや冷房による外からの冷えは、消化器系の中心である腸に直接的な影響を与え、本来の働きを妨げてしまいます。夏は体力を消耗しやすく、胃腸も疲れやすい季節。そこに冷えが加わることで、腸はますます疲弊し、「腸疲れ」の状態に陥ってしまうのです。
腸の冷えが引き起こす体の不調とは
「腸が冷える」と聞くと、お腹が痛くなることだけを想像するかもしれません。しかし、腸の冷えは単なるお腹の不調にとどまらず、全身に様々な影響を及ぼします。あなたのその不調、もしかしたら夏の腸の冷えが原因かもしれません。
以下に、腸の冷えが引き起こす主な体の不調をまとめました。
| 不調のサイン | 腸の冷えとの関連性 |
|---|---|
| 下痢や便秘を繰り返す | 腸の動きが鈍くなり、消化吸収能力が低下することで、便通が不安定になります。 |
| お腹の張りやガスが溜まる | 冷えにより腸内環境が乱れ、悪玉菌が増えることでガスが発生しやすくなります。 |
| 食欲不振や消化不良 | 胃腸の機能が低下し、食べ物をうまく消化吸収できなくなるため、食欲がわきにくくなります。 |
| 全身のだるさや疲労感 | 腸は栄養吸収の要。機能低下はエネルギー不足につながり、体が重く感じられます。 |
| 免疫力の低下 | 腸には体の免疫細胞の約7割が集まっています。冷えは免疫機能の低下を招き、風邪を引きやすくなります。 |
| 肌荒れや吹き出物 | 腸内環境の悪化は、老廃物の排出を妨げ、肌のトラブルとして現れることがあります。 |
| 肩こりや頭痛 | 血行不良が全身に波及し、特に首や肩周りの筋肉が硬くなりやすくなります。 |
これらのサインに心当たりがある方は、夏の腸疲れが原因である可能性が高いです。早めに適切な対策を講じることで、これらの不調を改善し、快適な夏を取り戻すことができるでしょう。
夏の腸冷えを解消 温め薬膳の基本
夏の暑い時期は、ついつい冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎたり、エアコンの効いた部屋で過ごす時間が長くなりがちです。しかし、それが原因で知らず知らずのうちに腸が冷え、様々な不調を引き起こすことがあります。この章では、なぜ夏に腸が冷えるのか、そしてその冷えを解消するために薬膳の知恵がどのように役立つのかを詳しく解説します。
なぜ夏に腸が冷えるのかそのメカニズム
夏は外気温が高いため、体は体温を下げようと働きます。しかし、現代の生活ではその働きを阻害する要因が多く存在します。
- 冷たい飲食物の過剰摂取:冷たい飲み物やアイスクリーム、かき氷などは、一時的に体を冷やしてくれますが、直接胃腸を冷やし、消化機能を低下させます。これにより、食べたものの消化吸収が滞り、腸への負担が増大します。
- エアコンによる冷え:室内と屋外の温度差が大きいと、体温調節を司る自律神経に負担がかかります。特に、お腹周りが冷やされることで、内臓の血行が悪化し、腸の働きが鈍くなることがあります。
- シャワーのみの入浴:湯船に浸からずシャワーだけで済ませる習慣も、体の深部まで温まらず、内臓の冷えを招きやすい要因となります。
これらの要因が複合的に作用することで、腸の働きが低下し、いわゆる「腸冷え」の状態が引き起こされます。腸が冷えると、消化吸収能力が落ちるだけでなく、免疫機能にも影響が出ることが知られています。
腸を温めることの重要性
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、私たちの健康を支える重要な臓器です。腸が冷えることで、以下のような様々な不調が引き起こされる可能性があります。
- 消化不良・便秘・下痢:腸の動きが悪くなることで、食べたものの消化吸収がうまくいかず、便秘や下痢、お腹の張りなどの症状が出やすくなります。
- 免疫力の低下:私たちの体の免疫細胞の約7割は腸に集中していると言われています。腸が冷えて働きが低下すると、免疫細胞の活性が落ち、風邪を引きやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりする原因となります。
- 疲労感・倦怠感:腸の機能が低下すると、栄養の吸収が悪くなり、体に必要なエネルギーが不足しがちになります。これにより、体がだるく感じたり、疲れが取れにくくなったりします。
- 自律神経の乱れ:腸と脳は密接に連携しており、腸の冷えや不調は自律神経のバランスを崩す原因にもなります。これは、睡眠の質の低下や精神的な不安定さにも繋がることがあります。
これらの不調を改善し、全身の健康を維持するためには、腸を温め、その働きを正常に保つことが非常に重要です。腸を温めることで、血行が促進され、消化吸収能力が向上し、免疫機能も高まります。
薬膳の知恵で体を内側から整える
薬膳は、食材が持つ「性味(せいみ)」という性質を理解し、季節や体質、体調に合わせて食材を選び、調理することで、体のバランスを整え、健康を維持・増進することを目指す中国伝統医学の考え方に基づいた食事法です。単に栄養を摂るだけでなく、食材の持つ効能を最大限に活かし、体を内側から温め、調和させることを重視します。
「温性」食材とはどんなもの
薬膳では、食材をその性質によって「温性(おんせい)」「熱性(ねっせい)」「平性(へいせい)」「涼性(りょうせい)」「寒性(かんせい)」の五つに分類します。この中で、体を温める作用を持つのが「温性」や「熱性」の食材です。夏の腸冷え対策には、特に「温性」の食材を積極的に取り入れることが推奨されます。
主な温性食材の例を以下に示します。
| 分類 | 温性食材の例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 野菜 | 長ねぎ、ニラ、しょうが、にんにく、かぼちゃ、ごぼう、玉ねぎ | 体を温め、血行を促進し、発汗を促す作用があります。特に香味野菜は冷え改善に有効です。 |
| 肉類 | 鶏肉、羊肉、牛肉 | 体を温め、滋養強壮に優れ、気力を補う作用があります。 |
| 魚介類 | 鮭、えび、あじ、いわし、カツオ | 体を温め、冷えを改善し、気血を補う作用があります。 |
| 穀物・豆類 | もち米、黒豆 | 体を温め、消化を助け、滋養を補います。 |
| 調味料・香辛料 | 味噌、唐辛子、シナモン、山椒、黒砂糖 | 体を温め、血行促進や消化促進に役立ちます。 |
これらの温性食材を日々の食事に取り入れることで、内臓の冷えを防ぎ、体全体を温めることができます。
薬膳における腸と免疫の関係
薬膳の観点からも、腸は非常に重要な役割を担っています。東洋医学では、腸は「脾(ひ)」や「胃(い)」の機能と深く関連しており、飲食物から栄養を吸収し、体を構成する「気(き)」「血(けつ)」「津液(しんえき)」を作り出す源と考えられています。これらのバランスが崩れると、体の抵抗力も低下するとされています。
現代医学においても、腸には全身の免疫細胞の約7割が集まっていることが明らかになっており、腸内環境が私たちの免疫力に大きく影響することが知られています。腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌がバランスを取りながら生息しており、この「腸内フローラ」のバランスが崩れると、免疫機能が低下しやすくなります。
腸が冷えると、腸の動きが悪くなり、腸内フローラのバランスが乱れやすくなります。悪玉菌が増殖しやすくなり、結果として免疫細胞の働きが鈍くなる可能性があります。薬膳では、温性食材を用いて腸を温め、消化吸収機能を高めることで、腸内環境を整え、免疫力を向上させることを目指します。また、発酵食品などを取り入れることで、善玉菌の活動を助け、より効果的に腸の健康をサポートします。
夏の“腸疲れ”に効く温め薬膳レシピ
夏の冷え切った腸を労り、内側から温めてくれる薬膳レシピをご紹介します。これらのレシピは、体を温める「温性」の食材を積極的に取り入れ、胃腸に負担をかけにくい調理法で、夏の疲れた体に優しく寄り添います。冷たいものの摂りすぎで滞りがちな血行を促進し、消化吸収を助けることで、腸の働きをサポートし、体全体の活力を取り戻すことを目指します。
長ねぎと鮭のホイル焼き 滋養たっぷり味噌風味
手軽に作れて栄養満点、そして何より体が温まる「長ねぎと鮭のホイル焼き」は、夏の夕食にぴったりの一品です。ホイルで包んで焼くことで、食材の旨味と栄養を逃がさず閉じ込め、ふっくらと仕上がります。
鮭と長ねぎの温め効果と栄養
このレシピの主役である鮭と長ねぎは、薬膳において体を温める「温性」に分類される食材です。特に、夏の冷えが原因で起こる胃腸の不調や、免疫力の低下を感じている方におすすめです。
| 食材 | 温め効果・薬膳的効能 | 栄養学的メリット |
|---|---|---|
| 鮭 | 体を温める温性食材。気血を補い、胃腸を丈夫にする働きがあります。冷えによる腹痛や消化不良の緩和に役立ちます。 | 良質な動物性タンパク質が豊富で、疲労回復をサポートします。DHAやEPAといった不飽和脂肪酸は血液をサラサラにし、ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、免疫力向上にも寄与します。 |
| 長ねぎ | 体を温める代表的な温性食材です。発汗作用があり、冷えによる初期の風邪症状や、血行不良による体のこわばりを和らげる効果が期待できます。 | 独特の辛味成分であるアリシンは、血行促進作用や殺菌作用を持ち、新陳代謝を高めます。ビタミンCも含まれており、抗酸化作用も期待できます。 |
| 味噌 | 体を温める発酵食品です。消化吸収を助け、腸内環境を整えることで、腸の冷えからくる便秘や下痢の改善に貢献します。 | 植物性タンパク質、乳酸菌、食物繊維、イソフラボン、ミネラルなど多様な栄養素を含み、腸活に非常に有効です。 |
簡単調理で夏の夕食にぴったり
ホイル焼きは、材料を切って包んで焼くだけなので、夏の暑いキッチンでの調理時間を大幅に短縮できます。フライパンやオーブントースターでも手軽に作れるため、火を使う時間を最小限に抑えたい夏に最適です。また、ホイルごと食卓に出せば洗い物も少なく、忙しい日でも気軽に薬膳を取り入れられます。味噌の風味は食欲をそそり、夏の疲れた体でも食べやすいでしょう。
ニラたっぷり!豚バラとキノコのスタミナ炒め
ニラと豚バラ肉、そしてキノコを組み合わせた炒め物は、夏の暑さで消耗した体に活力を与え、冷えがちな胃腸を内側から温めるスタミナ満点の一品です。薬膳では、ニラは「温性」の食材として知られ、体を温め、気の巡りを良くする効果が期待できます。
ニラのパワーで冷え知らずの体へ
ニラは、その独特の香りと共に体を温める作用を持つ代表的な温性食材です。特に、夏の冷たい飲食物の摂りすぎで体が冷え、消化機能が低下している場合に、胃腸の働きを活発にし、冷えの改善に役立ちます。
| 食材 | 温め効果・薬膳的効能 | 栄養学的メリット |
|---|---|---|
| ニラ | 体を温める温性食材。血行促進、気の巡りを改善し、冷え性や疲労回復に効果的です。特に、お腹の冷えによる下痢や腹痛の緩和に良いとされます。 | アリシン(硫化アリル)が豊富で、ビタミンB1の吸収を促進し、疲労回復に貢献します。ビタミンC、β-カロテン、食物繊維も含まれています。 |
| 豚バラ肉 | 体を温める温性食材。滋養強壮に優れ、夏の体力消耗を補うのに適しています。 | 良質なタンパク質と脂質、ビタミンB群(特にB1)が豊富で、疲労回復やエネルギー代謝を促進します。 |
胃腸に優しいキノコとの組み合わせ
このレシピでは、胃腸に優しいキノコをたっぷり加えることで、栄養バランスと消化のしやすさを両立させています。キノコ類は、低カロリーでありながら、豊富な食物繊維が腸内環境を整え、夏の腸活をサポートします。また、キノコの旨味成分は、炒め物全体の風味を豊かにし、食欲を増進させる効果も期待できます。油の使用を控えめにし、さっと炒めることで、胃腸への負担を軽減しながら、温かく滋養のある一品に仕上げましょう。
しょうが香る!鶏ひき肉と根菜の和風あんかけ
「しょうが香る!鶏ひき肉と根菜の和風あんかけ」は、体を芯から温めるしょうがと、食物繊維豊富な根菜を組み合わせた、夏の腸疲れに優しい薬膳レシピです。とろみのあるあんかけは、冷えがちな胃腸をじんわりと温め、消化吸収を助ける効果も期待できます。
しょうがの温め効果を最大限に引き出す
しょうがは、薬膳において「温性」に分類され、体を温める効果が非常に高いことで知られています。特に、夏の冷房や冷たい飲食物による体の冷え、消化不良に効果を発揮します。このレシピでは、しょうがをたっぷりと使うことで、その温め効果を最大限に引き出します。
| 食材 | 温め効果・薬膳的効能 | 栄養学的メリット |
|---|---|---|
| しょうが | 体を温める代表的な温性食材。血行促進、発汗作用、消化促進に優れています。冷えによる胃腸の不調や、食欲不振の改善に役立ちます。 | ジンゲロールやショウガオールといった辛味成分が、血流を良くし、新陳代謝を高めます。殺菌作用や抗炎症作用も持ち合わせています。 |
| 鶏ひき肉 | 体を温める温性食材。気血を補い、胃腸を丈夫にする働きがあります。消化しやすく、夏の疲れた体にも優しいタンパク源です。 | 低脂肪で高タンパク質であり、必須アミノ酸をバランス良く含んでいます。ビタミンB群も豊富で、疲労回復をサポートします。 |
根菜で食物繊維もプラス
ごぼう、れんこん、にんじんなどの根菜は、薬膳では体を温める性質を持つものが多く、特に食物繊維が豊富で腸内環境の改善に役立ちます。夏の腸疲れは、冷えだけでなく、食生活の乱れによる便秘や下痢も原因となることがあります。根菜の食物繊維は、腸の蠕動運動を促し、善玉菌のエサとなることで、健康な腸内フローラを育みます。あんかけにすることで、根菜が柔らかく煮込まれ、消化しやすくなるため、胃腸への負担も軽減されます。しょうがの香りが食欲をそそり、温かいあんかけが冷え切った体を優しく包み込みます。
温め薬膳レシピをもっと楽しむコツ
ご紹介した温め薬膳レシピをさらに効果的に、そして美味しく楽しむためのコツをご紹介します。日々の食事に少しの工夫を加えるだけで、夏の腸疲れ対策をより強化することができます。
薬味やスパイスで風味と温め効果アップ
薬膳では、食材が持つ「性味」を理解し、適切に組み合わせることが重要です。温め効果を高めるためには、料理に温性の薬味やスパイスを積極的に活用しましょう。
例えば、七味唐辛子、山椒、シナモン、クローブなどは、体を温める作用が強いスパイスです。あんかけや炒め物に少量加えるだけで、風味が増すだけでなく、血行促進効果も期待できます。また、みょうがや大葉、ねぎの青い部分なども、体を温めたり、消化を助けたりする効果を持つ薬味として活用できます。これらの薬味やスパイスは、食欲を刺激し、夏の食欲不振の改善にも繋がります。
発酵食品をプラスして腸活を加速
腸の健康は、体全体の免疫力と密接に関わっています。夏の腸疲れ対策として、温め薬膳レシピに加えて、発酵食品を積極的に摂り入れることで、腸活をさらに加速させましょう。
味噌、醤油、納豆、漬物、甘酒、ヨーグルトなどは、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えるプロバイオティクスが豊富です。これらの食品を日々の食事にプラスすることで、消化吸収が促進され、腸の冷えによる不調の改善に役立ちます。例えば、温かい味噌汁を毎食摂る、納豆を副菜にする、食後に甘酒を飲むなど、無理なく続けられる形で取り入れてみてください。温かい発酵食品は、腸を温めながら腸内環境を整えるため、一石二鳥の効果が期待できます。
お腹を温める生活習慣
食事で内側から温めるだけでなく、外側からもお腹を温めることで、腸の働きをサポートし、冷えによる不調を和らげることができます。特に、おへその周りには多くの臓器が集まっており、ここを温めることは全身の血行促進にもつながります。
- 腹巻きの活用: 夏場でも薄手の綿やシルク素材の腹巻きを着用することで、エアコンの冷気からお腹を守り、内臓の冷えを防ぐことができます。寝る時にも着用すると、寝冷え対策にもなります。
- 湯船に浸かる習慣: シャワーだけでなく、毎日湯船に浸かることで、体の芯から温まり、血行が促進されます。38~40度くらいのぬるめのお湯に、15~20分程度ゆっくり浸かるのがおすすめです。リラックス効果も高まり、自律神経のバランスを整えることにもつながります。
- 使い捨てカイロの利用: 特に冷えを感じる時には、使い捨てカイロをおへその下あたりに貼るのも効果的です。ただし、低温やけどには十分注意し、直接肌に貼らず、衣類の上から使用しましょう。
- エアコンの冷え対策: 冷房の効いた室内では、直接冷たい風がお腹に当たらないように、薄手のカーディガンやブランケットなどを活用しましょう。設定温度を極端に下げすぎないことも大切です。
まとめ
夏の暑さでつい冷たいものを摂りすぎ、知らず知らずのうちに腸が冷え切っていませんか?腸の冷えは、消化不良や免疫力の低下など、様々な不調を引き起こす原因となります。今回ご紹介した長ねぎ、鮭、にら、しょうがといった温性食材を積極的に取り入れた薬膳レシピは、体を内側からじんわり温め、夏の腸疲れを効果的にケアします。食事だけでなく、冷たい飲み物を控える、お腹を温める習慣、適度な運動など、日々の生活習慣を見直すことも大切です。これらの対策を組み合わせることで、腸の働きを整え、夏の不調を乗り越え、健やかな毎日を送ることができるでしょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
気になる記事、見つかるかも?
-

【夏の不調を改善】“7月病”って何?夏のやる気低下を防ぐ薬膳的アプローチと、気と心を補う鶏むね肉・なつめ・クコの実レシピ
梅雨明けから猛暑にかけて、「なんだか体がだるい」「やる気が出ない」と感じることはありませんか?それは「7月病」かもしれません。この夏の不調は、薬膳では「気」と… -



冬季うつ対策の決定版!薬膳レシピで心身を整える
冬の寒さとともに気分の落ち込みやだるさを感じる「冬季うつ」にお悩みではありませんか?この記事では、短い時間で要点を理解できるよう、冬季うつ対策として効果が期… -



デッドスペース解消!100均の「粘着フック+ワイヤーネット」活用術でシンク下スペースに吊るす裏技
シンク下のデッドスペース、有効活用できていますか?実は、100均(ダイソー、セリア、キャンドゥ)の粘着フックとワイヤーネット、そしてニトリの便利グッズを組み合わ… -



12月から始める免疫UP!風邪・インフルが増える冬の家族薬膳。子どもと大人が一緒に食べられる自宅でできる“免疫スープ”
12月から本格化する風邪やインフルエンザの流行。家族みんなで元気に冬を乗り切りたいけれど、毎日の食事で何ができるか悩んでいませんか? この記事では、なぜ今「冬の… -



年末の“疲れが抜けない”問題に終止符!「1日5分でできる冬の回復ルーティン」
「年末なのに、なんだか体がだるい」「疲れが抜けない」「毎日ぐったり…」そんな不調を感じていませんか?多忙な年末のストレスと冬の寒さは、知らず知らずのうちに私た… -



この時期キッチンの火を使う作業が地味に辛い…そんなあなたに贈る!夏も快適美味しいレシピ集!
夏のキッチン、火を使う作業が地味に辛いと感じていませんか?熱気がこもる台所での調理は、この時期特に億劫ですよね。この記事では、そんなあなたの悩みを解決すべく…