
「食欲の秋」を健康的に過ごしたいあなたへ。本記事では、実りの秋に旬を迎える食材と、心身のバランスを整える薬膳の知恵を組み合わせることで、季節の変わり目の不調を改善し、健やかな毎日を送る方法を徹底解説します。体を潤し温める秋の薬膳食材の選び方から、冷えや乾燥、疲労に効く簡単絶品薬膳ごはん5選まで、今日から実践できるヒントが満載。旬の恵みを味わいながら、心と体を癒し、美しい秋を満喫しましょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
実りの秋とは?旬食材と薬膳で心と体を整える
秋は、豊かな実りがもたらされる季節。夏の暑さで疲れた体を癒し、冬に備える大切な時期でもあります。この季節の変わり目を健やかに過ごすために、古くから伝わる知恵が「薬膳」です。そして、その薬膳の力を最大限に引き出すのが、まさに今が旬の「旬食材」たち。「実りの秋を味わう“旬食材×薬膳”」は、単なる食事ではなく、心と体を深く癒し、健やかな毎日へと導くための特別なアプローチなのです。
実りの秋の魅力と、体への影響
「実りの秋」と聞くと、多くの人が豊かな収穫を思い浮かべるでしょう。色とりどりの果物や野菜、そして海の幸が食卓を彩り、食欲をそそります。しかし、実りの秋の魅力は、食の豊かさだけではありません。心地よい涼しさ、澄んだ空気、紅葉の美しさなど、五感を通して季節の移ろいを感じられる時期でもあります。
この時期は、夏の間に溜まった熱を排出し、冬に向けてエネルギーを蓄える、体にとって非常に重要な「移行期間」です。季節の変わり目は体調を崩しやすいと言われますが、それは体が新しい環境に適応しようと頑張っている証拠。だからこそ、この時期に意識的に体を労り、整えることが大切なのです。
旬食材が持つ、体へのやさしい恵み
旬の食材は、その時期に最も栄養価が高く、生命力に満ち溢れています。自然のサイクルに合わせて育った旬の食材は、私たちの体のリズムとも深く共鳴し、季節の変わり目に必要な栄養素やエネルギーを効率よく供給してくれます。例えば、秋の果物には体を潤す効果が、根菜には体を温める効果が期待できるものが多いなど、その季節の体に必要な働きを自然と補ってくれるのです。旬の食材を積極的に取り入れることは、美味しく健康を維持するための、最もシンプルで効果的な方法と言えるでしょう。
薬膳の基本と、秋の養生
「薬膳」と聞くと、特別な食材や複雑な調理法を想像するかもしれませんが、実は日々の食事を通して体のバランスを整える、「医食同源」の考え方に基づいたものです。体質や体調、そして季節の変化に合わせて食材を選び、調理することで、病気になる前の「未病」の段階で体を整え、健やかさを保つことを目指します。
薬膳の知恵は、特定の病気を治療するものではなく、私たちの体が本来持っている自然治癒力を引き出し、心身の調和を促すことを目的としています。秋の薬膳では、乾燥しがちな体を潤し、冷えやすい体を温める食材を意識的に取り入れることで、季節の不調を予防し、快適に過ごすための土台を築きます。
旬食材×薬膳で心と体を癒す理由
旬の食材が持つ豊かな栄養と生命力に、薬膳が培ってきた体のバランスを整える知恵を組み合わせることで、私たちは季節の変わり目をより健やかに、そして美味しく乗り越えることができます。秋の旬食材は、まさにこの時期の体に必要な潤いや温かさをもたらし、薬膳の視点からそれらを組み合わせることで、より効果的に心と体を癒し、整えることが可能になります。このアプローチは、単に体の不調を改善するだけでなく、日々の生活に彩りを与え、心身ともに充実した「実りの秋」を味わうための鍵となるでしょう。
秋の薬膳で体質改善!季節の変わり目を健やかに過ごす知恵
実りの秋は、食欲の秋でもありますが、実は夏の疲れがどっと出やすく、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもあります。朝晩の冷え込みと日中の暖かさの寒暖差、そして空気の乾燥が進むことで、私たちの体は大きなストレスを受けています。このような季節の変わり目にこそ、薬膳の知恵を取り入れ、体の中から健やかに整えることが大切です。
薬膳は、日々の食事を通して体質を改善し、病気になる前の「未病」を防ぐという東洋医学の考え方に基づいています。秋の薬膳を知ることで、季節特有の不調を和らげ、冬に向けて万全の体調を整えることができるでしょう。
秋に起こりやすい体の不調と薬膳の考え方
秋は、中医学(東洋医学)において「燥(そう)」の季節とされています。空気の乾燥が進み、この「燥邪(そうじゃ)」が体に侵入しやすくなるため、様々な不調が現れやすくなります。
特に影響を受けやすいのが、中医学でいう「肺(はい)」です。肺は呼吸器系だけでなく、皮膚や粘膜、そして免疫機能とも深く関わっています。そのため、秋の乾燥は、肺の機能を低下させ、肌や喉、鼻などの不調を引き起こしやすくなります。また、夏の疲れが残っているところに、気温の低下が加わることで、胃腸の働きが弱まったり、冷えを感じやすくなったりすることも特徴です。
具体的に秋に起こりやすい体の不調と、それに対する薬膳の基本的な考え方をまとめました。
| 秋に起こりやすい体の不調 | 薬膳の考え方(中医学的視点) |
|---|---|
| 乾燥(肌の乾燥、髪のパサつき、喉の痛み、空咳、鼻の乾燥、便秘) | 「潤燥(じゅんそう)」:肺を潤し、体内の津液(しんえき:体液)を補い、乾燥から体を守る |
| 冷え(手足の冷え、お腹の冷え、胃腸の不調) | 「温補(おんぽ)」:体を温め、陽気を補い、冷えによる不調を改善する |
| 疲労・だるさ(夏の疲れ、季節の変わり目のだるさ) | 「補気健脾(ほきけんぴ)」:気を補い、脾胃(ひい:消化器系)の働きを整えてエネルギーを生み出す |
| 免疫力低下(風邪をひきやすい、アレルギー症状の悪化) | 「益肺固表(えきはいこひょう)」:肺を養い、衛気(えき:免疫力)を高めて外邪の侵入を防ぐ |
| 気分の落ち込み(なんとなく憂鬱、イライラ) | 「疏肝理気(そかんりき)」:気の巡りを良くし、精神的な安定を促す |
これらの不調は、一つだけでなく複数同時に現れることもあります。薬膳では、体の状態や体質に合わせて食材を選び、日々の食事からバランスを整えることを目指します。
【簡単】実りの秋を味わう!心と体を癒す絶品薬膳ごはん5選
実りの秋は、旬の食材が豊富に手に入り、食欲の秋でもあります。しかし、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもあります。そこで、薬膳の知恵を取り入れた「心と体を癒す絶品ごはん」で、健やかな秋を過ごしませんか? ここでは、手軽に作れて、日々の食卓に取り入れやすい薬膳レシピを5つご紹介します。 旬の食材の力を借りて、内側から元気に、そして美しくなりましょう。
冷えと乾燥に効く!きのこたっぷり鶏肉の薬膳スープ
秋の深まりとともに気になる冷えや乾燥。そんな時に体を芯から温め、潤いを与えてくれるのがこのスープです。数種類のきのこの旨味と鶏肉の滋養が溶け合い、心身ともにホッと安らぎをもたらします。体を温める生姜や長ねぎを加えることで、巡りを良くし、冷えからくる不調を和らげます。
| 主要食材 | 薬膳的効能 |
|---|---|
| 鶏肉 | 体を温め、気血を補う。疲労回復、胃腸の働きを助ける。 |
| きのこ(しいたけ、えのき、舞茸など) | 免疫力アップ、食物繊維が豊富で腸内環境を整える。 |
| 生姜 | 体を温め、発汗作用、胃腸の働きを助ける。 |
| 長ねぎ | 体を温め、発汗作用、風邪の初期症状緩和。 |
お好みでクコの実やなつめを加えると、さらに滋養効果が高まります。 煮込むことで食材の旨味が凝縮され、優しい味わいに仕上がります。風邪の引き始めや、体がだるい時にもおすすめです。
胃腸に優しい!鮭と秋野菜のホイル焼き
季節の変わり目は胃腸がデリケートになりがち。消化に良く、栄養満点の鮭と旬の野菜を組み合わせたホイル焼きは、胃腸に負担をかけずに栄養を摂取できる理想的な一品です。素材の旨味を閉じ込める調理法で、ふっくらと美味しくいただけます。鮭は体を温め、胃腸の働きを助ける効能があり、秋野菜と共に消化吸収をサポートします。
| 主要食材 | 薬膳的効能 |
|---|---|
| 鮭 | 体を温め、気血を補う。胃腸の働きを助け、疲労回復。 |
| 玉ねぎ | 消化促進、気を巡らせる。 |
| しめじ | 免疫力向上、食物繊維が豊富。 |
| パプリカ | ビタミンCが豊富で、体を潤し、免疫力アップ。 |
味噌や醤油麹で味付けすると、発酵食品の力でさらに胃腸に優しく、深いコクが生まれます。 ホイルで包んで焼くので、洗い物も少なく手軽に作れるのも嬉しいポイントです。
美肌効果も期待!さつまいもと蓮根の甘辛炒め
乾燥が気になる秋は、肌の潤いも意識したいもの。さつまいもと蓮根は、体を潤し、美肌をサポートする薬膳食材です。甘辛い味付けでご飯が進むだけでなく、食物繊維も豊富で、腸内環境を整える効果も期待できます。 腸内環境が整うことは、肌の調子にも直結します。
| 主要食材 | 薬膳的効能 |
|---|---|
| さつまいも | 体を潤し、脾胃(消化器系)を補う。便秘解消、美肌効果。 |
| 蓮根 | 体を潤し、熱を冷ます。止血作用、胃腸の働きを助ける。 |
| ごま | 体を潤し、便秘解消、アンチエイジング。 |
蓮根はシャキシャキ感を残すために、炒めすぎないのがポイント。仕上げに黒ごまを散らすと、香ばしさと共に薬膳効果もアップします。 お弁当のおかずにもぴったりです。
疲労回復に!薬膳カレー風味の豚肉とごぼうの煮物
夏の疲れが残りがちな秋は、疲労回復を促す食材を取り入れたいもの。豚肉は滋養強壮に優れ、ごぼうは気を巡らせる働きがあります。カレー風味にすることで、食欲をそそり、体を温める効果も期待できます。スパイスの香りが食欲を刺激し、消化を助けるため、食欲不振の時にもおすすめです。
| 主要食材 | 薬膳的効能 |
|---|---|
| 豚肉 | 体を潤し、気血を補う。疲労回復、滋養強壮。 |
| ごぼう | 気を巡らせ、デトックス効果。食物繊維が豊富で便秘解消。 |
| 玉ねぎ | 消化促進、気を巡らせる。 |
| カレー粉 | 体を温め、食欲増進、消化促進。 |
カレー粉は、ターメリック、クミン、コリアンダーなどのスパイスを組み合わせたもので、それぞれに薬膳的な効能があります。 煮込むことで、ごぼうの旨味が豚肉に染み込み、深みのある味わいになります。ご飯にかけても美味しくいただけます。
心も体も温まる!栗と生姜の炊き込みご飯
秋の味覚の代表格である栗は、体を温め、胃腸の働きを助ける優れた食材です。そこに体を温める生姜を加えることで、冷えやすい秋の体を内側からポカポカと温めてくれます。 ほくほくの栗と生姜の香りが食欲をそそり、心も体も満たされる一品です。栗は「腎」の働きを助け、足腰の冷えや疲れにも良いとされています。
| 主要食材 | 薬膳的効能 |
|---|---|
| 栗 | 体を温め、脾胃(消化器系)を補う。滋養強壮、腎の働きを助ける。 |
| 生姜 | 体を温め、発汗作用、消化促進。 |
| 米 | 気を補い、胃腸の働きを助ける。 |
生姜は細切りにして加えると、香りがより引き立ちます。 栗は下処理済みのものを使えば、手軽に作れます。秋の食卓を豊かに彩る、心温まる一品です。
もっと手軽に!実りの秋の薬膳を日常に取り入れるコツ
「薬膳」と聞くと、特別な食材や複雑な調理法を想像しがちですが、実は日々の食生活に簡単に取り入れられる方法がたくさんあります。実りの秋の恩恵を最大限に活かし、心と体を健やかに保つための手軽な薬膳のコツをご紹介します。
薬膳茶でほっと一息
食後や休憩時間に温かい薬膳茶を一杯飲むだけで、体の中からじんわりと温まり、秋の不調を和らげる効果が期待できます。市販のブレンド茶を活用したり、身近な食材を組み合わせて手作りしたりと、ライフスタイルに合わせて楽しんでみましょう。
特に秋におすすめの薬膳茶は、乾燥対策や体を温める効果が期待できるものです。以下に代表的な薬膳茶とその効能をまとめました。
| 薬膳茶の種類 | 主な効能 | 手軽な取り入れ方 |
|---|---|---|
| 生姜茶 | 体を温め、冷えや風邪の初期症状を和らげる。消化促進効果も。 | 市販の生姜パウダーやチューブ生姜をお湯に溶かす。紅茶に加えるのもおすすめ。 |
| なつめ茶 | 胃腸を整え、精神を安定させる。疲労回復や貧血予防にも。 | 乾燥なつめを煮出すか、市販のなつめ茶パックを利用する。 |
| ほうじ茶 | 体を温め、リラックス効果。胃腸に優しく、香ばしい風味で心を落ち着かせる。 | 日常的に飲んでいるお茶をほうじ茶に変える。 |
| 梨茶 | 体の熱を冷まし、喉の渇きや乾燥した咳を潤す。消化促進。 | 生の梨を薄切りにしてお湯に浸すか、乾燥梨を利用する。 |
| 白きくらげ茶 | 肺を潤し、肌や粘膜の乾燥を防ぐ。美肌効果も期待できる。 | 乾燥白きくらげを水で戻し、煮詰めて飲む。甘みを加えても美味しい。 |
これらの薬膳茶は、その日の体調や気分に合わせて選ぶのがおすすめです。例えば、朝の目覚めに生姜茶で体を温め、夜寝る前にほうじ茶でリラックスするなど、無理なく日常に組み込むことが継続の秘訣です。
身近な調味料で薬膳効果アップ
普段の料理に使っている調味料にも、実は薬膳的な効能を持つものがたくさんあります。いつもの料理に少し工夫を加えるだけで、手軽に薬膳効果を高めることができます。秋の薬膳におすすめの調味料と、その活用法を見ていきましょう。
| 調味料 | 薬膳的な効能 | 料理への取り入れ方 |
|---|---|---|
| 生姜 | 体を温め、発汗を促す。消化促進や吐き気を抑える効果も。 | 炒め物、煮物、味噌汁、スープに。魚や肉の臭み消しにも。 |
| 味噌 | 発酵食品。体を温め、消化吸収を助ける。腸内環境を整える。 | 味噌汁、和え物、炒め物の味付けに。 |
| ごま油 | 体を潤し、乾燥を防ぐ。便秘改善や滋養強壮に。 | 炒め物、和え物、ドレッシングに。仕上げに少量かけるだけでも効果的。 |
| はちみつ | 肺を潤し、喉の乾燥や咳を和らげる。滋養強壮、疲労回復。 | 飲み物、ヨーグルト、デザートに。料理の隠し味としても。 |
| 酢 | 疲労回復、消化促進。食欲増進効果も。 | 和え物、マリネ、ドレッシングに。煮物に入れると味がまろやかに。 |
| クコの実 | 滋養強壮、目の健康をサポート。体を潤し、免疫力向上。 | 炊き込みご飯、スープ、デザートのトッピングに。そのまま食べることも可能。 |
これらの調味料は、特別なものではなく、スーパーで手軽に手に入ります。例えば、いつもの味噌汁にすりおろし生姜を加えたり、サラダにごま油と酢をベースにしたドレッシングを使ったりするだけで、簡単に薬膳の知恵を日常に取り入れることができます。秋の食卓に、これらの調味料を意識的に取り入れて、体の内側から健やかさを育みましょう。
まとめ
実りの秋は、旬の食材が豊富に揃い、薬膳の知恵を取り入れる絶好の機会です。秋に起こりやすい乾燥や冷えといった不調には、「潤い」と「温め」を意識した食材選びが大切。今回ご紹介した「きのこたっぷり鶏肉の薬膳スープ」や「鮭と秋野菜のホイル焼き」など、簡単な薬膳ごはんを通じて、心と体を癒し、健やかに過ごすヒントをお届けしました。薬膳茶や身近な調味料の活用で、もっと手軽に日々の食卓に取り入れられます。ぜひ、秋の恵みを味わいながら、ご自身の体と向き合い、充実した毎日をお過ごしください。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
気になる記事、見つかるかも?
-

夏の疲れをリセット!秋に備えるボディケアは薬膳で決まり。カンタン薬膳レシピで体調管理
夏の暑さで溜まった疲れ、そのままにしておくと秋の不調につながることも。本記事では、そんな夏の疲れをリセットし、乾燥や風邪といった秋特有の体調変化に負けない体… -


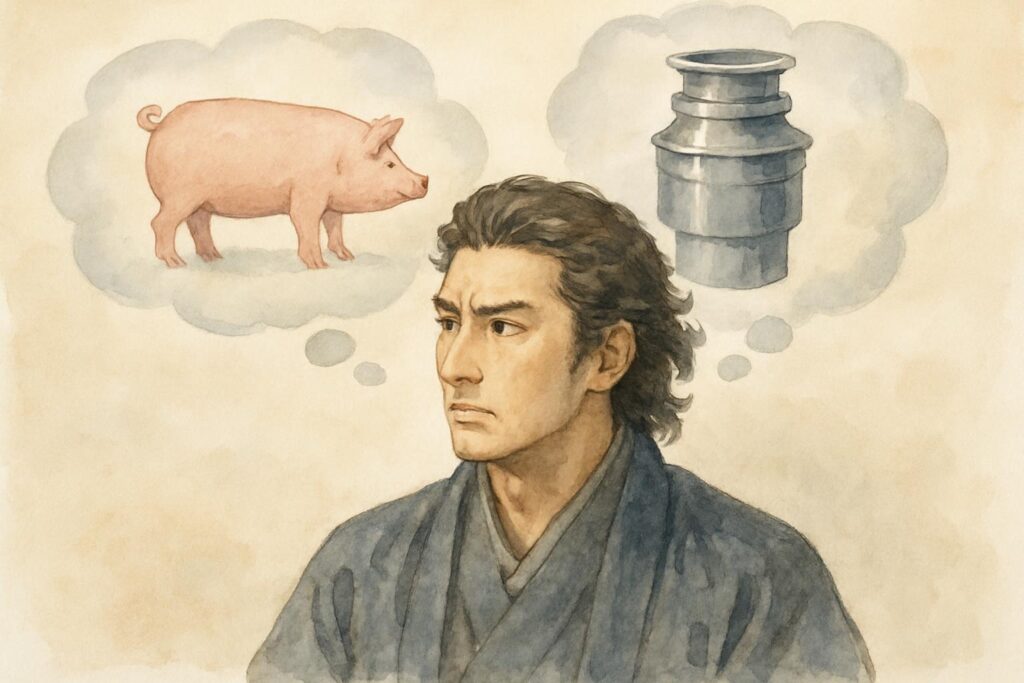
新撰組とディスポーザー!?土方歳三が挑んだ“ゴミ問題”と、現代キッチンの革命
「ディスポーザー」と聞いて、何を思い浮かべますか?実はこの“生ゴミ処理機”が、あの新撰組と意外な共通点を持っていたとしたら…? 今回は、NHKのある番組で紹介されて… -


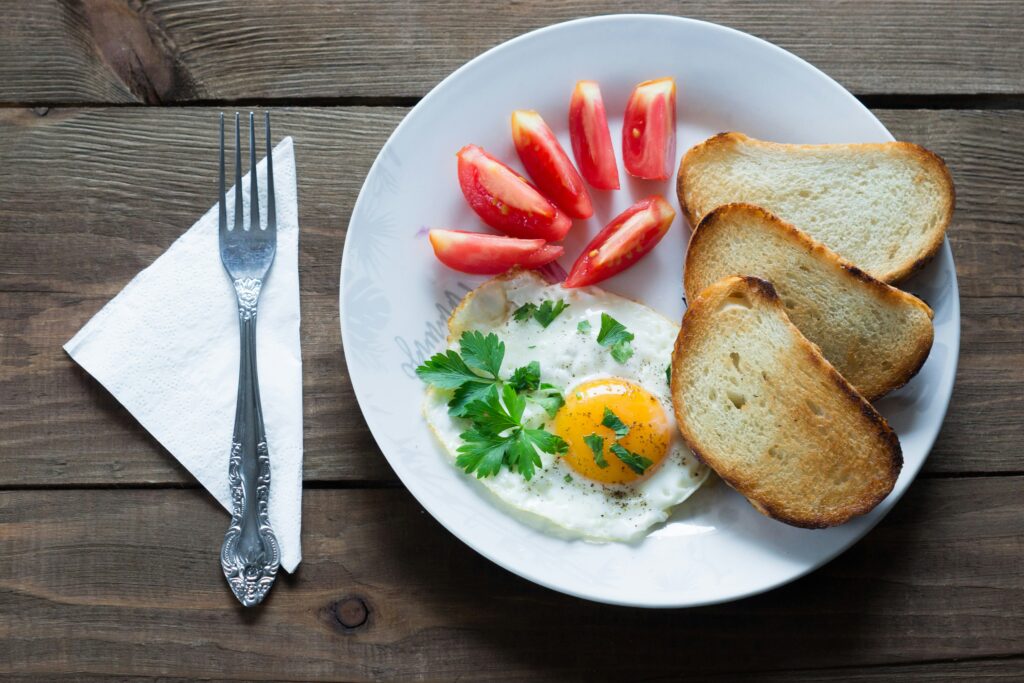
子育て中の朝食革命!「朝ごはんワンプレート作戦」すべてワンプレートにのせて洗い物1枚で済む時短に役立つ豆知識
子育て中の朝は時間との戦い。特に朝食の準備と山積みの洗い物にうんざりしていませんか?この記事では、そんな悩みを解決する「朝ごはんワンプレート作戦」を徹底解説… -



12月から始める免疫UP!風邪・インフルが増える冬の家族薬膳。子どもと大人が一緒に食べられる自宅でできる“免疫スープ”
12月から本格化する風邪やインフルエンザの流行。家族みんなで元気に冬を乗り切りたいけれど、毎日の食事で何ができるか悩んでいませんか? この記事では、なぜ今「冬の… -



今日からできる!秋の土用で始める「薬膳」生活の基本と実践レシピ
「秋の土用」は、夏の疲れが残りつつ、本格的な冬へと向かう季節の変わり目。この時期に「なんだか体がだるい」「肌が乾燥する」「風邪をひきやすい」と感じることはあ… -



時短&節約!夏野菜を賢く長持ちさせる冷凍保存術ガイド
旬の夏野菜を美味しく長持ちさせたいけれど、使いきれずに傷ませてしまうことはありませんか?この記事では、夏野菜を賢く冷凍保存し、鮮度を保ちつつ、時短と節約を叶…


