
梅雨明けから猛暑にかけて、「なんだか体がだるい」「やる気が出ない」と感じることはありませんか?それは「7月病」かもしれません。この夏の不調は、薬膳では「気」と「心」の消耗が原因と考えられます。本記事では、夏のエネルギー不足とメンタルダウンを防ぐ薬膳的アプローチを徹底解説。さらに、気と心を補う鶏むね肉、なつめ、クコの実を使った具体的なレシピもご紹介します。この記事を読めば、夏の不調を乗り越え、心身ともに健やかに過ごすためのヒントが見つかります。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
「7月病」とは?夏のやる気低下の原因と症状
梅雨が明け、本格的な夏が到来すると、多くの人が経験する「なんとなく体がだるい」「やる気が出ない」といった不調。これらは医学的な病名ではありませんが、一般的に「7月病」や「夏バテ」として知られる夏の特有の症状群です。特に梅雨明けから猛暑が続く時期に顕著になり、私たちの心身に様々な影響を及ぼします。
単なる疲れと見過ごされがちですが、放置すると日常生活に支障をきたすこともあります。この章では、この「7月病」がなぜ起こるのか、その原因と具体的な症状について、現代医学的な視点と薬膳の考え方を交えながら詳しく解説していきます。
梅雨明けから猛暑に増える「なんとなくだるい」の正体
梅雨明けの蒸し暑さから一転、容赦ない猛暑が続く日本の夏は、私たちの体に大きな負担をかけます。この時期に多くの人が訴える「なんとなくだるい」という感覚の裏には、複数の要因が絡み合っています。
- 自律神経の乱れ:急激な気温や湿度の変化に体が適応しきれず、体温調節を司る自律神経のバランスが崩れやすくなります。これにより、だるさや倦怠感が生じます。
- 体力の消耗:暑い環境下では、体は常に体温を下げようとエネルギーを消費します。また、大量の汗とともにミネラルやビタミンが失われ、肉体的な疲労が蓄積しやすくなります。
- 睡眠の質の低下:寝苦しい夜が続くと、深い睡眠が取れず、睡眠不足に陥りがちです。十分な休息が取れないことで、疲労が回復せず、日中のだるさにつながります。
- 冷房による体の冷え:室内と屋外の温度差が激しい環境に長時間いると、体は冷えすぎたり、逆に温まりすぎたりと、体温調節機能が麻痺しやすくなります。これが「冷房病」とも呼ばれ、だるさや胃腸の不調を引き起こすことがあります。
これらの要因が複合的に作用することで、私たちの体は「夏バテ」や「7月病」と呼ばれる状態に陥り、パフォーマンスの低下や不快な症状に悩まされるようになるのです。
現代医学と薬膳から見た「7月病」の主な症状
「7月病」の症状は多岐にわたりますが、ここでは特に多くの人が経験する代表的な症状を、現代医学と薬膳それぞれの視点から解説します。
| 症状名 | 現代医学的視点での特徴と原因 | 薬膳的視点での関連 |
|---|---|---|
| 疲労感や倦怠感 | 体が重く、何もする気が起きない、朝起きるのがつらいといった状態。暑さによる体力消耗、発汗によるミネラル・ビタミンの喪失、睡眠不足、自律神経の乱れなどが原因となります。 | 体に必要なエネルギーである「気(き)」が不足している状態(気虚)と考えられます。気が消耗すると、体はだるく、力が入らなくなります。 |
| 食欲不振や胃腸の不調 | 食欲がわかない、胃もたれ、下痢や便秘など。冷たい飲食物の摂りすぎ、消化酵素の働きが低下すること、胃腸の血管が収縮し血流が悪くなることなどが原因です。 | 飲食物の消化吸収を司る「脾(ひ)」と「胃(い)」の機能が低下している状態。湿気が多い環境も脾胃に負担をかけやすいとされます。 |
| イライラや気分の落ち込み | 些細なことで怒りっぽくなる、集中力が続かない、憂鬱な気分になる、不安感が募るといった精神的な症状。暑さによるストレス、睡眠不足、自律神経の乱れ、脳の疲労などが影響します。 | 精神活動を司る「心(しん)」が熱や消耗により不安定になっている状態(心火亢進、心血虚など)。気の巡りが滞ることでイライラが生じることもあります。 |
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数同時に経験することもあります。特に「やる気が出ない」という状態は、肉体的な疲労と精神的なストレスが複合的に作用していることが多く、単なる休養だけでは改善しにくい場合もあります。
薬膳から紐解く夏の不調「7月病」
夏の不調、特に「7月病」と呼ばれるような心身の不調は、現代医学的なアプローチだけでなく、古くから伝わる薬膳の知恵によっても深く理解することができます。薬膳では、私たちの体は「気(き)」「血(けつ)」「津液(しんえき)」という3つの要素がバランス良く巡ることで健康が保たれると考えられています。このバランスが崩れると、さまざまな不調として現れるのです。
特に夏は、暑さや湿気といった季節特有の環境要因が、体内の特定の臓腑や要素に大きな影響を与え、バランスを崩しやすくする時期とされています。「7月病」にみられるやる気の低下や倦怠感、食欲不振といった症状も、薬膳の視点から見ると、特定の要素の消耗や不足が原因であると捉えることができます。
「気虚」と「心血虚」夏のやる気低下の薬膳的視点
夏のやる気低下や倦怠感は、薬膳では主に「気虚(ききょ)」と「心血虚(しんけっきょ)」という二つの状態が重なり合って生じると考えられます。これらの状態は、それぞれ異なるアプローチで対処することが重要です。
| 状態 | 薬膳的定義 | 「7月病」における主な症状 |
|---|---|---|
| 気虚(ききょ) | 生命エネルギーである「気」が不足している状態。 | 全身の倦怠感、だるさ やる気が出ない、億劫に感じる 少し動くと息切れがする 声に力がない、小さい 食欲不振、胃もたれしやすい 風邪をひきやすい、抵抗力が弱い 汗をかきやすい(自汗) |
| 心血虚(しんけっきょ) | 「心」を養う「血」が不足し、「心」の機能が低下している状態。 | 不眠、寝つきが悪い、夢が多い イライラ、不安感、気分が落ち込む 動悸、息切れ 物忘れがひどい 顔色が青白い、唇の色が薄い めまい、立ちくらみ 手足のしびれ、こむら返り |
このように、「気虚」は主に身体的なエネルギー不足に起因するだるさや活動意欲の低下を、「心血虚」は精神的な不安定さや睡眠の質の低下に深く関わっています。夏の過酷な環境下では、これら両方の状態が複合的に現れることが多く、これが「7月病」の複雑な症状を引き起こすと考えられます。
「気」と「心」を補う!おすすめ薬膳食材
夏の「7月病」によるやる気の低下や体のだるさは、薬膳では主に「気」と「心」の消耗が原因と考えられます。ここでは、これらの重要な要素を補い、夏の不調を和らげるのに役立つおすすめの薬膳食材をご紹介します。
「7月病」対策に役立つ鶏むね肉の薬膳効果
鶏むね肉は、薬膳において「気」を補う代表的な食材とされています。消化吸収が良く、胃腸に負担をかけにくい特性を持つため、夏バテで食欲がない時や胃腸が弱っている時でも摂りやすいのが特徴です。
その薬膳的効能は以下の通りです。
- 補気健脾(ほきけんぴ):「気」を補い、消化吸収を司る「脾胃(ひい)」の働きを健やかにします。これにより、食べたものから効率よくエネルギーを作り出す助けとなり、疲労感や倦怠感の改善に繋がります。
- 益精填髄(えきせいてんずい):生命活動の源である「精(せい)」を補い、体を滋養する効果も期待できます。
低脂肪で高タンパク質な鶏むね肉は、夏の暑さで消耗した体力を回復させ、やる気を高めるための優れたエネルギー源となります。
「7月病」対策に役立つなつめの薬膳効果
なつめは、その甘味と栄養価の高さから「一日3個食べれば年を取らない」と言われるほど、古くから親しまれてきた薬膳食材です。特に「気」と「心」の両方を補う作用に優れています。
主な薬膳効果は以下の通りです。
- 補気養血(ほきようけつ):「気」を補い、同時に「血(けつ)」も養います。夏の暑さで消耗しやすい「気」と、発汗によって失われやすい「血」の両方を補給することで、疲労回復や貧血の改善に役立ちます。
- 養心安神(ようしんあんしん):「心」を養い、精神を安定させる作用があります。イライラや不安感、不眠など、夏のメンタルダウンに効果的とされています。
- 健脾和胃(けんぴわい):「脾胃」の働きを健やかにし、消化吸収を助けるため、食欲不振や胃腸の不調を和らげるのにも役立ちます。
そのまま食べたり、お茶に入れたり、料理に加えるなど、手軽に取り入れられるのも魅力です。
「7月病」対策に役立つクコの実の薬膳効果
クコの実は、その鮮やかな赤色からもわかるように、薬膳では「血」を補い、「肝」と「腎」を滋養する食材として重宝されます。「心」と密接に関わる「肝」を養うことで、精神的な安定にも繋がります。
その薬膳的効能は以下の通りです。
- 滋補肝腎(じほかんじん):「肝(かん)」と「腎(じん)」を滋養し、体の潤いを補います。これにより、目の疲れやかすみ、めまい、足腰のだるさなどの改善が期待できます。
- 養心安神(ようしんあんしん):なつめと同様に「心」を養い、精神を安定させる作用があります。イライラや不安感を鎮め、穏やかな気持ちをサポートします。
- 益精明目(えきせいめいもく):「精」を補い、目を明るくする効果があります。
なつめと一緒に薬膳茶にしたり、サラダやヨーグルトのトッピング、料理の彩りとしても活用できます。
【レシピ】「7月病」対策!気と心を補う薬膳レシピ
梅雨明けから猛暑にかけて、体がだるく、やる気が出ない「7月病」の症状に悩まされがちです。そんな時こそ、日々の食事から「気」と「心」を補い、体の中から元気を取り戻しましょう。ここでは、「7月病」対策に特化した、鶏むね肉、なつめ、クコの実を活用した薬膳レシピをご紹介します。どれも手軽に作れて、体と心に優しいものばかりです。
鶏むね肉と夏野菜のさっぱり炒め
「気」を補う代表的な食材である鶏むね肉と、夏の体に嬉しい旬の野菜を組み合わせた、消化に優しくさっぱりと食べられる一品です。疲労回復にも役立ちます。
材料と作り方
| 材料(2人分) | 分量 |
|---|---|
| 鶏むね肉 | 1枚(約250g) |
| きゅうり | 1本 |
| ナス | 1本 |
| パプリカ(赤・黄) | 各1/4個 |
| 大葉 | 5枚 |
| 生姜(みじん切り) | 1かけ |
| ごま油 | 大さじ1 |
| 【A】醤油 | 大さじ1.5 |
| 【A】みりん | 大さじ1 |
| 【A】酒 | 大さじ1 |
| 【A】鶏ガラスープの素(顆粒) | 小さじ1/2 |
作り方:
- 鶏むね肉は薄切りにして、酒(分量外)少々をもみ込みます。きゅうり、ナス、パプリカは食べやすい大きさに切ります。大葉は千切りにします。
- フライパンにごま油と生姜を熱し、鶏むね肉を炒めます。色が変わったらナス、パプリカ、きゅうりの順に加えて炒めます。
- 全体に火が通ったら、【A】の調味料を加えて炒め合わせます。
- 器に盛り付け、大葉を散らして完成です。
薬膳ポイント
鶏むね肉は「気」を補い、体のエネルギー不足を改善するのに優れた食材です。夏バテによる疲労感やだるさの解消に役立ちます。また、きゅうりやナス、パプリカといった夏野菜は、体の余分な熱を冷まし、夏にこもりやすい熱邪(ねつじゃ)を取り除く効果が期待できます。大葉は「気」の巡りを良くし、生姜は胃腸の働きを助け、食欲不振の改善にもつながります。これらの食材の組み合わせは、夏のやる気低下や食欲不振といった「7月病」の症状に総合的にアプローチします。
なつめとクコの実入り薬膳スープ
「心」を養い、精神を安定させる効果が期待できるなつめとクコの実をたっぷり使った、心身を癒す優しいスープです。胃腸にも負担をかけず、じんわりと体に染み渡ります。
材料と作り方
| 材料(2人分) | 分量 |
|---|---|
| 鶏もも肉(または鶏むね肉) | 100g |
| なつめ(乾燥) | 5〜6個 |
| クコの実 | 大さじ1 |
| しめじ | 1/2パック |
| 長ねぎ | 1/2本 |
| 水 | 600ml |
| 鶏ガラスープの素(顆粒) | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| ごま油(仕上げ用) | 少々 |
作り方:
- なつめは軽く洗って種を取り除きます。クコの実を水で軽く戻しておきます。鶏肉は一口大に切り、しめじは石づきを取りほぐします。長ねぎは斜め薄切りにします。
- 鍋に水と鶏肉、なつめを入れ、中火で煮ます。アクが出たら取り除きます。
- 鶏肉に火が通ったら、しめじと長ねぎ、鶏ガラスープの素を加えて煮込みます。
- 野菜が柔らかくなったらクコの実を加え、塩で味を調えます。
- 器に盛り付け、お好みでごま油を数滴垂らして完成です。
薬膳ポイント
なつめは「気」と「血」を補い、精神を安定させる効果があります。イライラや気分の落ち込みといった「心」の不調に悩む方におすすめです。クコの実は「心血」を養い、滋養強壮に優れているとされます。両方を組み合わせることで、夏の暑さで消耗しやすい「心」をしっかりとサポートし、不安感や不眠の改善にも寄与します。鶏肉も「気」を補うため、夏の疲労回復に相乗効果をもたらします。消化に良いスープは、食欲不振の際にも栄養を摂りやすいメリットがあります。
薬膳レシピ以外でできる「7月病」対策
「7月病」による夏の不調は、薬膳的なアプローチだけでなく、日々の生活習慣や心のケアによっても大きく改善が期待できます。ここでは、特別な食材や調理法を必要としない、誰でも手軽に始められる対策をご紹介します。
生活習慣の見直しで心身を整える
夏の暑さや湿気は、私たちの自律神経のバランスを乱し、心身に大きな負担をかけます。規則正しい生活を送ることで、体のリズムを整え、夏の不調を和らげることができます。
質の良い睡眠を確保する
睡眠は、疲労回復の基本です。寝苦しい夏こそ、質の良い睡眠を確保することが重要です。就寝前にぬるめのお風呂に浸かる、寝室の温度や湿度を適切に保つ、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控えるなど、リラックスできる環境を整えましょう。規則正しい時間に就寝・起床することで、体内時計が整い、自律神経の安定にも繋がります。
適度な運動を取り入れる
夏は暑さで運動がおっくうになりがちですが、軽い運動は血行を促進し、気分転換にも効果的です。早朝や夕方など涼しい時間帯に、ウォーキングやストレッチ、軽いヨガなどを取り入れてみましょう。無理のない範囲で継続することが大切です。ただし、大量の汗をかくような激しい運動は、かえって「気」を消耗する原因になることもあるため注意が必要です。
冷房と上手に付き合う
夏の室内は冷房が効きすぎて体が冷えやすい環境です。体が冷えすぎると、血行不良や胃腸の不調に繋がります。冷房の風が直接当たらないように工夫したり、薄手の羽織ものやブランケットを活用して、体を冷やしすぎないように注意しましょう。特に、首元、お腹、足元を冷やさないように心がけることが大切です。
生活習慣を見直す際のポイントを以下の表にまとめました。
| 見直し項目 | 具体的な対策 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 睡眠 | 規則正しい就寝・起床時間 寝室の温度・湿度管理(25~28℃、湿度50~60%目安) 就寝前のリラックスタイム(入浴、ストレッチなど) | 疲労回復 自律神経の安定 免疫力向上 |
| 運動 | 早朝や夕方のウォーキング、ストレッチ 無理のない範囲で継続 | 血行促進 気分転換 ストレス軽減 |
| 冷房対策 | 直接風が当たらない工夫 薄手の羽織もの、ブランケットの活用 体を温める飲み物(白湯など) | 冷えによる不調の予防 血行不良の改善 胃腸の保護 |
リラックスできる時間を作りメンタルケア
「7月病」では、イライラや気分の落ち込みといったメンタル面の不調も多く見られます。心にゆとりを持ち、ストレスを上手に解消する時間を作ることで、精神的な安定を図りましょう。
趣味や好きなことに没頭する
自分の好きなことに没頭する時間は、最高の気分転換になります。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、絵を描く、ガーデニングなど、どんなことでも構いません。日常のストレスから一時的に離れ、心をリフレッシュさせましょう。
瞑想や深呼吸を取り入れる
短時間でも良いので、静かな場所で瞑想したり、ゆっくりと深呼吸を繰り返すことで、心を落ち着かせることができます。深呼吸は、副交感神経を優位にし、リラックス効果を高める作用があります。数分間でも毎日続けることで、心の状態が安定しやすくなります。
自然と触れ合う機会を増やす
公園を散歩したり、ベランダで植物を育てたりと、自然に触れる機会を増やすこともメンタルケアに有効です。緑や水の音、土の香りなどは、私たちの心を癒し、穏やかな気持ちにしてくれます。ただし、日中の強い日差しは避け、熱中症には十分注意しましょう。
デジタルデトックスを試す
スマートフォンやパソコンから離れる時間を作る「デジタルデトックス」も、心の疲れを癒すのに役立ちます。情報過多な現代において、意識的にデジタル機器から距離を置くことで、脳を休ませ、集中力を高める効果も期待できます。
まとめ
「7月病」は、梅雨明けから猛暑にかけて「気」と「心」が消耗し、心身のバランスが崩れることで生じる夏の不調です。だるさややる気の低下を感じたら、薬膳的アプローチが有効。鶏むね肉、なつめ、クコの実などの食材で「気」と「心」を補い、食生活と生活習慣を見直すことで、夏の不調を乗り越え、健やかな毎日を過ごしましょう。
この記事を書いた人

石倉 るみ (公式アンバサダー)
薬に頼らず整える薬膳🌿
栄養士歴18年、薬膳料理教室を主宰するママ栄養士です。
スポーツ栄養インストラクターとして、
家庭でも実践できる「簡単薬膳」を発信しています。
軽度ADHDの息子を育てる中で、心と体を整える食卓の大切さを実感。
同じように頑張る方々に寄り添いながら、健やかな毎日を支える食を提案しています。
【体質別相談はこちら】
ホルモン美人メソッド
LINE
気になる記事、見つかるかも?
-

同時蒸し?蒸し器なし調理の究極ガイドで時短・絶品レシピ
「同時蒸し」に興味はあるけれど、専用の蒸し器がないと無理だと思っていませんか?ご安心ください。この究極ガイドでは、特別な道具がなくても、ご家庭の鍋、フライパ… -



【40代女性必見】冬の“肌荒れ・粉吹き”を食べて改善!冬食材で美肌薬膳
冬の厳しい寒さと乾燥は、40代女性の肌に深刻なダメージを与えがち。「鏡を見るたびに、肌の乾燥、赤み、粉吹きにため息…」「化粧ノリが悪くて、気分まで落ち込む」そん… -



メンタルが揺れる冬に!心を整える薬膳と温活習慣で、気温差×日照不足で気が乱れやすい日々を改善。
冬になると、なんとなく気分が沈んだり、イライラしたり、疲れやすくなったり…といった「メンタルが揺れる」状態に心当たりはありませんか?その不調の背景には、冬特有… -



【100均・ニトリ】上から見える軽量カップが便利すぎ!たれ&ドレッシング作りが劇的に変わる活用術
「たれやドレッシング作りが面倒…」「計量カップが使いにくい…」そんな悩みを解決してくれるのが、上から目盛りが見える軽量カップです。この記事では、100均(ダイソー… -



【冷蔵庫・保存テクニック】忙しいあなたへ!<週末仕込み>切った根菜を水にさらして冷蔵 → 平日すぐ使える賢い時短テクニック
「平日の料理をもっと楽にしたい」そんなあなたへ。この記事では、週末に切った根菜を水にさらして冷蔵するだけで、鮮度を保ちつつ平日すぐに使える時短テクニックを徹… -


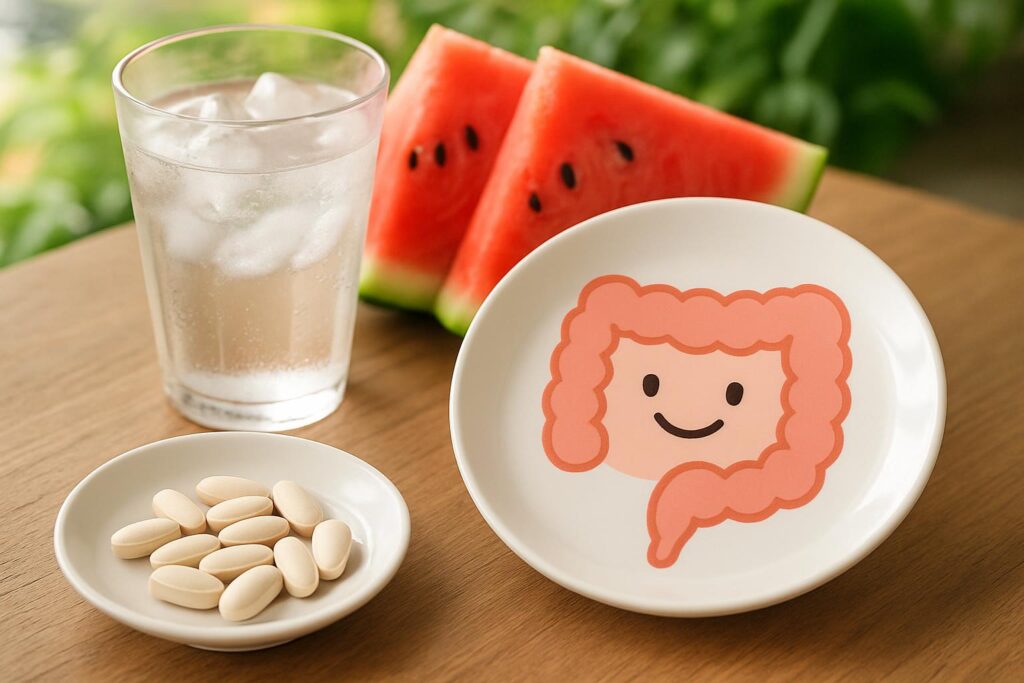
冷え切った腸に喝!夏の“腸疲れ”に!冷えすぎ防止の温め薬膳レシピで元気を取り戻す
夏の暑さで冷たいものを摂りすぎ、腸が冷えて「腸疲れ」を感じていませんか?お腹の不調やだるさは、冷えすぎた腸からのSOSかもしれません。この記事では、なぜ夏に腸が…


